-
本日の発売はありません
- 尼崎GⅠ

- 丸亀GⅢ


- 三国一般

- 鳴門一般

- からつ一般

- 戸田一般

- 平和島一般

- 常滑一般

- 児島一般

- 桐生一般

- 若松一般













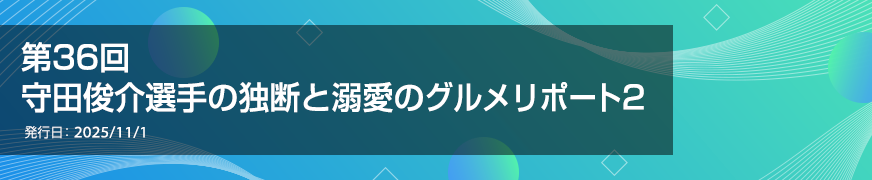
『氷の女王の下僕の日記』
こんにちは(__)
早いもので2025年ももう秋を過ぎようかとしています。
ヤバいです、ホンマに。まだめちゃくちゃ暑いです。9月なのに滋賀の夜も暑い。
今まで生きてきて経験した事ないかも?の暑さ警戒レベルです。
そうなればもう氷しかないですよね?体温下げるために食べな死ぬわこれ!!と言いながら、
わたくしは皮下脂肪なしで寒がりのガリガリの体なので、
氷食べながらいつも「寒い!寒い!」を連呼しては妻の太陽さんにウザがられてますが・・・笑
まずは数年前、石山で見つけた『根っこ』さんをご紹介します。
普段は夜、居酒屋なのですが昼間の営業でかき氷をやってくれてます。
これがまた見た目も味もセンスあってヨカですよ!(^^)!
とりあえずね、もう全部うますぎてたまらんのやけど美味しそうに撮れたやつを全部載っけておきますので
皆さんコーフンして暴発?してくれたら幸いです。
まず最初は「マンゴー杏仁」でパイナップル、ココナッツチップが添えられ、
マンゴーソース、ヨーグルトソースに杏仁クリームの豪華な競演です。
互いのソースが上手く混じり合い抜群のハーモニーを奏でます。
続いては数量限定の「桃」です。
ほんのり甘い桃の果肉に桃ソースをかけ、グラノーラ、桃コンポート、
ミルクシロップ、濃厚なカスタードソースを包み込みます。
三つ目は「ほうじ茶チョコレート」。
ほうじ茶の香りとチョコレートの控えめな甘さの競演で、ほうじ茶シロップにクリームチーズクリーム、
見た目は分かりづらいですがブドウに黒豆、黒糖クルミが添えられチョコレートソースのかかるにぎやかな味です。
とりあえず、もう全部うますぎて、撮れたやつ全部載っけますヽ(^o^)丿
根っこさんに出会ってからここ数年、毎年欠かさず通ってますので、是非皆さんも!!




続いては『ちんと』さん。
太陽さんがかき氷渦にハマって最初の頃に見つけたお店で、
開店したての3年くらい前からずっと通ってるお気に入りのお店です。
鼻が弱く、嗅覚素人レベルの僕でも見た目の良さ、素材の使い方、味の出し方、
総合レベルの高さを感じとれる逸品となっております。こちらも予約困難な人気店です。
ひとつ目は「あんず桃」です。
あんずピューレに桃と白ワインのコンポート。パッション果肉ソースとミルクシロップがけです。
添えるクリームはレアチーズ、ヨーグルト、酒かすクリームからひとつセレクトします。
二つ目は「とうもろこし」。
とうもろこしピューレにとうもろこしのつぶ、キャラメルクリームを添えて、プリンを少々。
ここにカレーナッツ、ブラックペッパーミルクシロップ、
パッション果肉をまぶして、これまた忘れられない衝撃のお味です。



最後はやっぱりもう1回紹介させてください。
瀬田の超有名店『カフェ フクバコ』さんです。
もう、全国的に有名になりすぎて予約取れません(´;ω;`)ネット予約マジで1秒でパンクします。
夫婦二人でスマホ3台並べて必死に予約戦争参加してるけど取れません(涙)
フクバコさんの事は一昨年のレポートも参照にしてください。
今回はまず、「フルーツバスケット」。これでもかの果肉がふんだんに盛りつけられてますね。
頂上のマンゴープリン。
そこからはレアチーズソースやパッションフルーツ、数種のピューレが加わり、
ドラゴンフルーツ、パイナップル、オレンジブルーベリーを盛り上げてくれます。
ミルクシロップが仕上げの味付けですね。とにかく豪華です。
続いては「やきいもみるく」です。
焼き芋、黒ゴマプリンとクランブルを添えてやきいもソースとカラメルソース、ミルクシロップで味を引き締めます。
いつもながらの安らぎのお味ですね。
太陽さんがかき氷渦にハマり早5年、何やかんやそれにお供してわたくしも5年。
冗談抜きで太陽さんは累計で多分3000杯以上食ってます。
これはマジ話です。特に最初の3~4年くらいの年間何百杯ペースが本気でエグかった…Σ(・□・;)
“ゴーラークイーン”氷の女王レベルです。
『太陽やけど氷の女王??』でいいと思います(笑)
そんな太陽さんにお供して僕も数百杯、もしかしたら1000杯を超えてるかも?
ボートレーサーの中ではダントツで食ってるかもしれませんね。
というわけで、今回のタイトルは『氷の女王の下僕の日記』でした。



| No. | 発行日 | タイトル |
|---|---|---|
| 第36回 | 2025/11/01 | 守田俊介選手の独断と溺愛のグルメリポート2 |
| 第35回 | 2025/08/18 | 湖東三山編その2 |
| 第34回 | 2025/06/05 | 湖東三山編その1 |
| 第33回 | 2025/03/19 | 守田俊介選手の独断と溺愛のグルメリポート |
| 第32回 | 2025/01/20 | 堅田・琵琶湖大橋編 |
| No. | 発行日 | タイトル |
|---|---|---|
| 第28回 | 2023/12/04 | 今話題の『かき氷』 |
| 第27回 | 2023/09/08 | 沖島 |
| 第26回 | 2023/06/05 | 八幡山城跡 |
| 第25回 | 2023/03/15 | 佐竹恒彦選手のお勧めスポット紹介 |
| No. | 発行日 | タイトル |
|---|---|---|
| 第24回 | 2022/12/23 | 清水未唯選手のお勧めスポット紹介 |
| 第23回 | 2022/10/13 | 守田俊介選手のお勧めスポット紹介 |
| 第22回 | 2022/07/28 | 青木玄太選手のお勧めスポット紹介 |
| 第21回 | 2022/03/28 | 佐和山城探訪 |
| 第20回 | 2022/01/06 | 小谷城跡探訪 |
| No. | 発行日 | タイトル |
|---|---|---|
| 第19回 | 2021/11/10 | 姉川周辺から小谷城跡 |
| 第18回 | 2021/08/25 | 大溝城跡探訪 |
| 第17回 | 2021/03/01 | 安土城跡探訪 |
| 第16回 | 2021/01/29 | 長浜歴史旅 |
| No. | 発行日 | タイトル |
|---|---|---|
| 第15回 | 2020/12/31 | 坂本歴史旅2 |
| 第14回 | 2020/10/30 | 坂本歴史旅 |
| 第13回 | 2020/01/24 | 【4828 松山将吾】信楽 |
| No. | 発行日 | タイトル |
|---|---|---|
| 第12回 | 2019/10/07 | 【3721 守田俊介】滋賀のラーメン特集 |
| 第11回 | 2019/07/20 | 【4743 木村仁紀】びわ湖バレイ |
| 第10回 | 2019/04/22 | 【3606 川北浩貴】彦根城 |
| 第9回 | 2019/02/03 | 【番外編】かど萬祝勝会 |
| No. | 発行日 | タイトル |
|---|---|---|
| 第8回 | 2018/11/18 | 【4120 柘植政浩】甲賀の里忍術村 其の二 |
| 第7回 | 2018/10/13 | 【4120 柘植政浩】甲賀の里忍術村 其の一 |
| 第6回 | 2018/06/13 | 【4686 丸野一樹】栗東トレーニングセンター |
| 第5回 | 2018/04/09 | 【3721 守田俊介】湖北路をドライブ |
| 第4回 | 2018/01/01 | 【4502 遠藤エミ】大津のパン屋さん |
| No. | 発行日 | タイトル |
|---|---|---|
| 第3回 | 2017/10/13 | 【4448 青木玄太】琵琶湖のお魚料理と青木玄太 |
| 第2回 | 2017/07/01 | 【3582 吉川昭男】酒処「近江」と吉川昭男 |
| 第1回 | 2017/04/01 | 【3721 守田俊介】びわこ写真紀行! |